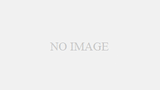インターネット上の発言には「これは誹謗中傷だ」と感じる内容がある一方で、法的には「単なる意見」として扱われるケースもあります。表現の自由と名誉権のバランスが問われる今、企業としてもこの線引きを正しく理解することが不可欠です。この記事では、“誹謗中傷”と“単なる意見”の違いについて、法律的な観点からわかりやすく解説します。
「誹謗中傷」とは?名誉毀損や侮辱に該当する表現とは
「誹謗中傷」とは、他人の名誉や社会的信用を不当に傷つける言動を指し、法律上では主に名誉毀損罪・侮辱罪・信用毀損罪・業務妨害罪といった罪名で処理されます。ここで重要なのは、「誹謗中傷」という言葉自体は法律用語ではなく、一般的にはこれらの複数の違法行為をひとまとめにした概念であるということです。
名誉毀損が成立する条件は、以下の3点です:
- 公然と事実を摘示したこと(不特定多数に向けた発信)
- その内容が人の社会的評価を低下させる性質を持つこと
- 摘示された事実が真実かどうかにかかわらず、公益性がないこと
たとえば、「この会社は違法行為をしている」「代表が詐欺師だ」といった断定的な投稿は、たとえ事実であっても名誉毀損に該当する可能性があります。特に、発信の目的が公益とは無関係であり、悪意があると判断されれば、違法性が強まります。
侮辱罪においては、事実を摘示する必要はなく、「バカ」「ゴミ企業」「死ねばいい」などの感情的・抽象的な表現であっても、人格攻撃と受け取られる発言は処罰対象となります。
企業がネット上でこれらの投稿を見つけた際は、「批判か誹謗中傷か」を感覚ではなく、法律の構成要件に基づいて判断することが重要です。違法性の有無は、投稿の“内容”と“発信方法”の双方に強く依存する点を押さえておきましょう。
「単なる意見」として保護される表現の具体例
一方で、「不快に感じる表現」であっても、それが法的に“単なる意見”として表現の自由の範囲内にあるとされることも多くあります。これは憲法第21条により保障された表現の自由とのバランスの問題であり、誰かの発言が必ずしも違法となるわけではないことを意味しています。
たとえば、以下のような表現は、原則として「単なる意見」として扱われます:
- 「このサービスは自分には合わなかった」
- 「対応が冷たく感じた」
- 「もう二度と利用しないと思う」
- 「あまりおすすめできないと感じた」
これらはあくまで個人の主観に基づいた感想であり、社会的評価を直接的に貶める内容ではありません。また、特定の個人や企業を名指ししておらず、限定的な文脈で述べられている場合も、違法性は認められにくくなります。
重要なのは、「批判=誹謗中傷」ではないという点です。企業にとって耳の痛い意見であっても、それが冷静な言葉で建設的に語られている限り、削除対象とはなりにくいのが現実です。
法的に削除請求を通すためには、単なるネガティブな感情表現ではなく、「虚偽性・侮辱性・拡散性」が揃っている必要があります。逆に言えば、企業としてはネガティブな声全てに神経質になる必要はなく、受け止めるべき批判と戦うべき誹謗中傷を峻別することが求められます。
判断のカギは“事実の有無”と“社会的評価への影響”
誹謗中傷か単なる意見かを判断するうえで、最も重視されるのが**「事実の摘示があるかどうか」と「社会的評価にどれだけ影響を与える内容か」**という2つの軸です。
まず「事実の摘示」とは、発信者が何か具体的な出来事や状況を断定的に述べているかどうかを指します。たとえば、「〇〇社は顧客から金を騙し取った」「社員が暴力をふるっている」などは、真実かどうかにかかわらず事実の摘示に該当します。
一方、「〇〇社は信用できない」「雰囲気が悪かった」といった表現は、明確な事実を示すものではなく、個人の感想・価値判断の領域に留まるため、法律的には保護される可能性が高くなります。
次に、「社会的評価への影響」も重要な判断材料です。内容が公の場で広く拡散され、企業や個人の信頼・地位に悪影響を及ぼすと認められれば、それだけ違法性が高まります。仮に私的な場での限定的な発言であっても、それがSNSや掲示板で拡散されてしまえば、社会的なダメージは計り知れません。
また、投稿の“言葉選び”も判断に影響を与えます。丁寧な口調であっても内容が名誉毀損にあたることはありますし、逆に乱暴な言葉でも社会的評価に直結しない場合は侮辱の範囲にとどまることもあります。
つまり、「法的に誹謗中傷かどうか」は投稿者の意図ではなく、受け取る側の社会的立場や影響の度合い、言葉の選び方と拡散状況によって変わるという点を理解しておく必要があります。
境界線が曖昧なときの対応と専門家の活用方法
現実の誹謗中傷問題の多くは、法的に「明らかに違法」と言い切れない“グレーゾーン”に位置します。そのため、企業が対応に迷ったときは、感情ではなく客観的な基準と専門的な判断をもとに行動することが重要です。
まずは、投稿内容と状況を整理し、「どこまでが事実で、どこからが意見なのか」「拡散の範囲」「過去に似た表現が削除された例があるか」などを把握します。この段階では、証拠の確保も非常に大切です。投稿のスクリーンショット、投稿日時、URL、コメント数などを記録しておきましょう。
それでも判断がつかない場合には、IT・ネット分野に強い弁護士や風評被害対策を行っている専門企業への相談が有効です。弁護士は、投稿が名誉毀損や侮辱にあたるかを法的観点から判断し、削除請求や開示請求が可能かどうかを教えてくれます。ネット対策企業は、法的に動けない投稿でも、逆SEOやモニタリングで印象をコントロールすることができます。
企業がすべきことは、「無闇に削除を迫る」のではなく、「正しく対応するための判断材料と体制を整える」ことです。曖昧な状況に冷静に向き合い、専門家の力をうまく借りることで、トラブルの長期化や二次炎上を防ぐことができるのです。
まとめ
「誹謗中傷」と「単なる意見」の境界は、時に非常に曖昧です。しかし、法律上は“事実の摘示”と“社会的評価への影響”を軸に判断され、主観的な不快感だけでは違法性が認められないケースも多くあります。企業としては、感情に流されず冷静に投稿の性質を見極め、必要であれば専門家の判断を仰ぎながら、法に則った適切な対応を進めることが信頼を守る第一歩となります。